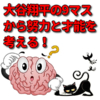新しい笑いを作る松本人志は本当に悪者か?
お笑いの種類

お笑いの種類を5つに分類
【お笑いの種類】という定義は難しいのですが、私の独断でお笑いを5つの種類に分けました。
- 漫才
- コント
- 落語
- 大喜利
- 一発芸
という感じです。
お笑いの定義
漫才の定義
漫才とは、2人が1組のコンビになり、基本として1人が「ボケ」もう1人が「ツッコミ」となり、掛け合い言い合いながら人を笑わせる演芸の1つです。
後ほど、漫才の定義を少し変えて話そうと思いますが、とりあえず基本はこれ。
歴史は長く、平安時代からある伝統芸能だそうです。
漫才は、
- しゃべくり漫才
- コント漫才
の2つに大きく分けられます。
キャラ漫才やシステム漫才と言われるものもあるようですが、基本はこの2つからの派生です。
コントの定義
コントとは、掛け合い言い合いの他に、物を使ったり、舞台セットを作ったりして、ドラマ仕立てのように個々の人が役を演じながら人を笑わせる演芸の1つです。
コント芸の基本としては、漫才のように「ボケ」と「ツッコミ」はあるのですが、特に人数に制限が無く、3人(トリオ)から4人5人と様々な人数で、コント芸は行われます。
漫才も実は人数制限が無かったりして、最近では3人漫才をやる若手が出てきたらしいですね。
昔から漫才は2人でやるものと、ルールを決めなくてもそういうもんだろって、昔の人の粋なところなのでしょうか。
落語の定義
落語とは、噺(はなし)って難しい字を書くんですが、ストーリー性のある噺の最後に落ち(オチ)がある伝統芸能です。
落語家さんのことを「噺家」さんと言われているのを聞いたことがあると思いますが、落語の「話し」は「噺(はなし)」なんです。
こんな言い方をしたら怒られるかもしれませんが、1人漫才と言うと理解しやすいかもしれません。
ストーリーの中で何人かの登場人物が出てくるのですが、その人たちが掛け合いをし、ボケたりツッコミ入れたり、それを1人で行い、最後に大きくオチを付ける、という感じ。
漫才の定義の前に、落語から説明するべきだったのかもしれませんが、漫才のオチもコントのオチも、この落語のオチからきています。
オチの定義を簡単に説明するのは難しいのですが、
- 笑い
- 驚き
- 感動
- 教訓
などで最後に大きく締めるものです。
実際、オチの種類は凄く多いので、単純にこの4パターンというわけじゃありません。
凄く単純に言ってしまえば、「最後の締め」がオチです。
酒を飲んだ時の最後のラーメンのような・・・違うか。
大喜利の定義
大喜利とは、2種類の意味があり、本来の意味としては「演目の最後の演芸」が大喜利となっています。
現代では、一般的に大喜利と言うと、笑点の大喜利のコーナーで行われている、
これが一般的に浸透している大喜利です。
まぁ笑点の人達が大喜利の定義を変えてしまったとも言えるでしょう。
凄いですよね!
一発芸の定義
一発芸とは、一瞬で笑わせる演芸の1つです。
一発芸の歴史はわかりませんが、昔から瞬間芸というものがあります。
瞬間芸の一つに「ものまね」もあります。
この瞬間芸が発展したものか、派生したものか、という感じでしょうか。
一発芸と言えば、志村けんさんが印象深いですよね。
『アイぃ~ん!』
2種類のお笑いトーク術
以前、明石家さんまさんの「さんまのまんま」という番組に、松本人志さんがゲストで来た時に、
明石家:「俺たちよく比較されんねんけど、全く別もんやからなぁ」
松本 :「そうですよねぇ~」
というやり取りがあったんです。
確か、こんなやり取りだったと思います。
この違いを深く考えたんですが、 トークのベースになっているものが違うという結論を、私は出しました。
その違いとは、漫才をベースにしたトークと、大喜利をベースにしたトーク。
明石家さんも松本さんも、両方とも漫才トークもするし大喜利トークもするのですが、ベースが違うんですよね。
スポーツに例えると、サッカーとラグビーが良いかもしれません。
同じような広さの四角いグランドで、同じような人数で走りながら、ボールをゴールに運ぶ。
しかし、使ってるボールの形も違うし、ゴールも違うし、ルールも違う。
それを、どっちが面白い競技かを比較しているようなもので。
スポーツでは全く違う競技として認識されているけど、お笑いでは同じトークでも全く違うと認識されない。
まぁお笑いの方が、違いがわかり難いとは思うのですが。
漫才トーク
上記で、漫才の定義をボケとツッコミと書いたのですが、これは見る側の定義であって、漫才をする側の定義としては、半分正解で半分間違いです。
漫才をする側の定義としては、「ネタ振り」と「オチ」に意識を持たないと、漫才のネタとしての面白さは半減すると言っても良いでしょう。
なので、漫才師が漫才を作っている過程で、ボケとツッコミという面白さだけを感じながら作っても、ネタとして通すとそれほど客にウケない。
ネタ振りとオチに強い意識を持って作らないと、ネタとしての面白さが増してこないんです。
ネタ振りとオチは疲れる
このネタ振りとオチが成立するためには、一所懸命しゃべらないといけない。
喋って喋ってネタ振りを広げてオチに持っていく。
明石家さん曰く、
「ネタ振りの振り幅が大きければ大きいほど、オチた時の笑いも大きなんねん」
ということ。
そのネタ振りを大きくするために、たくさん喋るんです。
だから、明石家さんのように良く喋る人が、漫才トークに向いているのでしょう。
大喜利トーク
いわゆる大喜利というのは、お題が出て回答なんで、ネタ振りが無いんです。
もちろん、前のトークをネタ振りにしてオチにする場合もあるのですが、基本はネタ振りも無く、
- 誰かが言った言葉
- 誰かに話しかけられた言葉
- 誰かがした行動
などに、一発で回答し、笑いに変える。
これって、一所懸命喋りまくってる明石家さんに比べて、凄くスマートに見えて、カッコ良く見えて、憧れてしまうんでしょうね。
お笑い芸人の勘違い
明石家さんのトークが凄すぎて、
「あれは真似できん」
と思うのか、
「あんなに喋るのは疲れるし、松本さんみたいにスマートに笑い取った方が省エネやん」
と、松本さんの芸の方が簡単そうに見えるのか、松本さんの芸を真似る芸人さんが、多いんですよね。
どっちが簡単というのは無いけど、どっちが難しいかと言えば、松本さんの方が断然難しいいということに気付いてない。
芸人は大きな勘違いをし続けてるんです。
悪者にされた松本人志
今でもたまに囁かれるような話しですが、
「今の笑いを変えてしまったのはダウンタウンの松本人志だ!」
と、笑いを変えてしまった松本さんを悪者かのように言う人がいます。
しかしダウンタウンや松本人志さんは、ただ新しい笑いを生み出しただけなのです。
若手が、そこに憧れ芸人になり、似たような芸をするのは、ごく自然なことでしょう。
しかし、プロの芸人になったからには、この松本さんの芸が、実際にどれほど難しく才能が無ければ無理な芸なのか、気付かなければいけません。
最初はモノマネのように、松本さんのような芸をしていても仕方ありませんが、数年芸人をやっていたら気づくべき部分です。
自分の実力を勘違いし、自分の努力に疑問を持たず、間違った方向で努力をしていなければ、必ず気付くべき部分なのに、気付けない。
このまま時代が流れてしまったことで、不幸にも「松本さん悪者説」になっていったのでしょう。
禁断の果実
もちろん、松本さんに憧れ、同じような芸でテレビに出て人気者になりたい、と思う事は否定しません。
あんなスマートに笑いを取れたら、そりゃカッコ良いですからね。
しかし、それがプロとして現実的かということには気づかなければいけない。
ネタ振りをせずに笑いを取る、大喜利トークをベースにするということが、どれだけ難しく才能がいることか、ということに気付かなければいけません。
フリ幅が無ければ、笑いは大きくなりようが無い。
ネタ振りも無く爆笑が取れるなんて、そりゃ才能しか無いでしょ。
笑点の面白さの秘密を、ここでバラすのはやめておきますが、笑点の大喜利メンバーですら、大喜利で爆笑なんて年に数回です。
お笑い芸人は、そこに気付くべき。
かと言って、ネタ振りをする漫才トークをしても、明石家さんには勝てないでしょう。
しかし、いずれ上の人達も歳を取り、力も衰え引退します。
その時に残っている芸人が、どっちのトークをベースにしているかということで、テレビの未来は大きく変わってしまうでしょう。
この大喜利トークを自分の武器にするというのは、禁断の果実なのです。
いずれ自分たちの、先の時代の芸人達に、毒が回ってしまうのです。