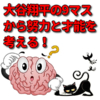【音楽用語】音楽理論とは?
音楽理論とは?
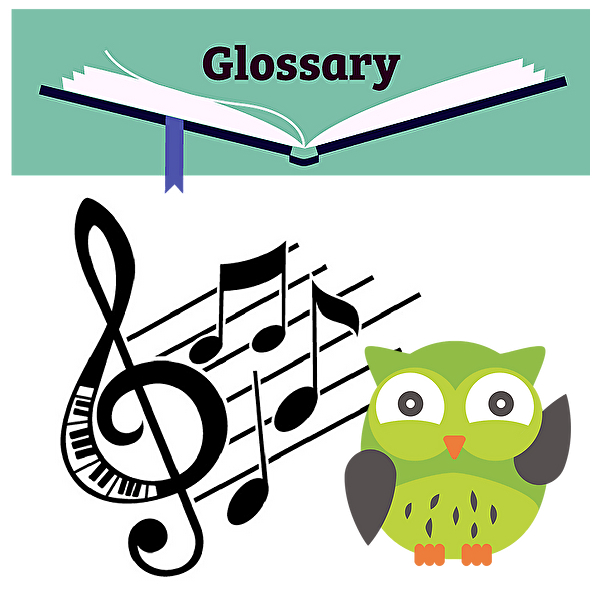
理論とは?
理論の意味は、辞書には、
「個々の現象を法則的、統一的に説明できるように筋道を立てて組み立てられた知識の体系」
と出ています。
正直、頭の悪い私には、「何言ってんだ?」って感じなんですが・・・
理論の意味を分かりやすく
『個々の現象を法則的』というのは、『個々の決まりや規則』のようなもの。
『統一的に説明できる』というのは、『まとめ』のような感じ。
『筋道を立てて組み立てられた知識の体系』というのは、『仕組みや順序立てたもの』と言う感じでしょうか。
理論を簡単に説明すると、と簡単に説明したのですが、簡単には説明できませんよね。。
「個々に規則を決めてまとめた知識を1つの仕組みとして順序立てたもの」
という感じでしょうか。
辞書の説明よりは、分かりやすくなったのではないでしょうか。
音楽理論の意味
音楽理論とは、
「音楽に規則を決めて、まとめた知識を1つの仕組みとし、順序立てたもの」
という感じですかね。
音楽理論って、この言葉の意味から難しいので、まずこの意味が理解できないと、音楽理論が理解出来なかったり必要なのかの判断も難しいんですよね。
音楽理論に挫折する理由
なぜ音楽理論は難しいの?
たぶん、私が少し簡単にした音楽理論の意味でも、まだ何のことだかさっぱり分からないと思います。
しかし、初心者の方は心配いりません。
音楽理論は、自分で何となく理解できていても、プロのミュージシャンや音楽教師でさえも、説明するのは難しいことなんです。
言葉の意味だけなら、私のように説明すれば済むのですが、音楽理論を理解してもらうとなると、
- 説明することが多い
- 知らないと理解できない言葉が多い
- 覚える必要がある項目が多い
- 用語によって例えるものが違う
ということで、挫折してしまう人も少なくありません。
って、初心者の方が、余計心配になってしまったら、ごめんなさい。
用語によって例えるものが違うので混乱
音楽理論を難しくしている理由の1つとして、用語によって例えるものが違うということがあります。
どういうことかと言うと、
| 音階 | ピアノの鍵盤 |
|---|---|
| ディグリーネーム | 楽譜の五線譜 |
というように、ピアノの鍵盤上での音で説明したり、楽譜の五線譜上で説明したり、これで混乱するわけです。
ピアノの鍵盤上での音の上がり方と、五線譜上での音の上がり方は、単純に1つ音が上がる時でも違う表記や上がり方になります。
なぜ音楽理論は必要なの?
音楽理論を勉強しようとする人の多くが、コード進行を理解するためです。
コード進行を理解しようとすると、音楽理論の理解が必要になってくるというわけです。
私のようにバンド音楽をメインで行っているのであれば、コード進行はそれほどというか、全く無くても作曲はできます。
しかし、
- プロを目指す
- プロのような作曲がしたい
- 話題になるような曲を作りたい
など、プロでもアマチュアでもそれなりに売れる曲や人気の曲を作るとなると、コード進行を意識して作曲するべきということです。
音楽理論の理解に必要な用語
コード進行を理解するためには、音楽の基礎知識から専門的な知識まで覚える必要があります。
基礎知識
- 音程
- 音階
- 和音
- Key
- 短調・長調
- オクターブ
など。
なんとなく音楽の時間に習ったことがあるけど、しっかり理解は出来てないという人も少なくありません。
専門知識
- スケール
- ディグリーネーム
- ダイアトニックコード
- ドミナントモーション
- 基本コード進行
など。
用語
初心者の方が音楽理論を理解するために、1つの用語を理解しようとすると、別の用語の意味や理解が出来てないと、次に進めない場合が多いです。
コード進行については、下記のページも参考にしてください。
まとめ
音楽理論が理解できるまでの期間
私のように、音楽の知識もロクに無い状態で勉強しようとすると、よほど頭が良くないと1回で覚えるなんて難しいでしょう。
音楽の専門家でも難しいわけですから。
私の場合、同じ本や動画やサイトなどを3回~5回ずつは見たり読んだりしています。
それでも理解しきれてはいないでしょう。
私の場合は、ある程度の理解ができるまでに1年くらいかかりましたが、早い人なら3ヵ月~半年くらいは考えても良いのではないでしょうか。
音楽理論を理解するには?
音楽理論は、簡単に理解できるものとは考えず、じっくり気長に理解を深めていくと考えた方が良いでしょう。
これが理解できたから良い曲が作れるというわけでは無いので、曲を作りながら勉強し続けることが大事です。
音楽理論が理解できてくると、クラッシックの定番曲や、ポップスのヒット曲などが、どんなコード進行で作られて、自分がどんな曲のコードの流れに魅了されるのかが分かってきます。
そして、自分がどんなコードの流れで曲を作りたいのか、などの方向性が出来てきます。
なので、音楽理論の理解は曲を作りながらで良いでしょう。
音楽理論に慣れること
音楽理論には、ピアノの鍵盤と楽譜の五線譜での説明が出てくるので、この2つに慣れることも必要です。
ピアノが弾けない人でも、五線譜がすらすら読めない人でも、ピアノや五線譜を理解するには慣れるしかありません。
これに慣れてくれば、混乱もだいぶ少なくなってきます。
パッと頭の中でイメージするのがピアノ?五線譜?というのは、音楽の勉強をしている人に比べると初心者には難しいので、焦らず気長に慣れていきましょう。